
❷市内在住外国人への防災施策について
最近、市内にお住まいの外国人の方をよく見かけるようになりました。
しかし、地域の防災訓練などに参加される機会もなく、言葉の壁があるなかで、きちんと必要な情報が届いているのかを質問しました。
まず、市内在住外国人の方の人数をお聞きすると
令和3年は1,111人、令和7年3月末時点では1,613人
と、約1.5倍に増えていることがわかります。
そのような外国人の防災施策でいうと「外国人支援のための避難所・医療機関マップ」があり、漢字にルビが振られた日本語版と、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語版が、市のHPに掲載されています。
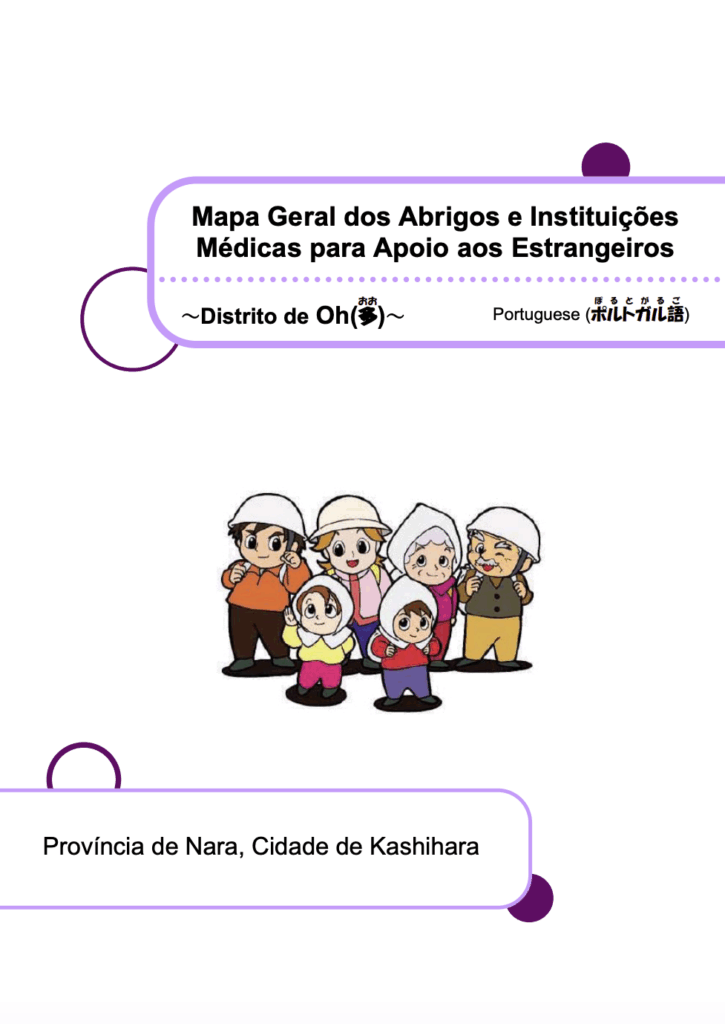
これをどのように外国人の方に配布しているのかを質問すると
「市のホームページでの公開のみで、直接配布は行われていない」との回答でした。
私からは、昨年奈良県が行った「奈良県内在住外国人住民アンケート」を紹介。
その中で「災害が起こったときのためにどのような準備をしているか」という問いに、「水や食料を準備している」44%の次に、「なにもしていない」と回答した方が32.8%と多いこと、しかもこれを市町村別で見ると、橿原市に住む外国人で「なにもしていない」と回答した人の率は40.7%で、奈良市の32.8%や生駒市の31.4%などと比べても多いことを指摘しました。
早急に対策が必要で、特に
「災害時に必要となるマップなどの防災情報を転入時にお渡しできないか」
同時に「現在多くなっているベトナム人、ネパール人向けの言語へ翻訳」を提案。
市は「転入時の配布と言語を増やすことを検討する」という回答でした。
また今年度、新しい橿原市地域防災計画を策定する予定になっており
「外国人向けの防災施策を計画にしっかりと記載しておくことが必要不可欠」と提案。
市は、現在の地域防災計画に、外国人への対応に関する記載がないことに触れ
「外国人に向けた情報提供のあり方に加え、外国人向けの防災研修の実施、地域の自主防災組織が実施する防災訓練への外国人の参加呼びかけなど、外国人向けの防災施策に関する記述を検討する」
と回答がありました!
ーーーーーーーーーーーーーーー
解説☝️
日本は災害が多いことから、普段から防災情報に触れていますが、外国の方はそういった経験や知識がないことが多いです。
万が一の際の混乱を最低限にするためにも、情報の周知が必要です。
また、より積極的な施策として「外国人防災リーダーの養成」を行っている岡山県総社市の例を、質問の中で触れさせていただきました。
外国人の方自らが防災について学び、伝えていくリーダーとなっていただく取り組みで、実際平成30年の西日本豪雨の際には、救助活動などにも参加されたとのことです。
総社市へは、今年5月に私の所属する総務常任委員会の行政視察で訪れています。
その時の視察は別テーマだったのですが、市役所内を見学した際、庁舎内に外国人の方の相談を受け付ける窓口があり、日本に帰化されたという外国にルーツを持つ職員さんが対応されていました。
その際、普段から在住外国人との共生社会の取り組みに熱心というお話を伺っていたので、確かにあの市なら、という思いが浮かびました。


外国人の方をかやの外に置いて、遠くから呼びかけるだけのような施策より、日本人と外国人、または外国人同士で気軽に声を掛け合えるような、本当の意味での多文化共生の防災施策が、今後実現することを期待したいと思います。